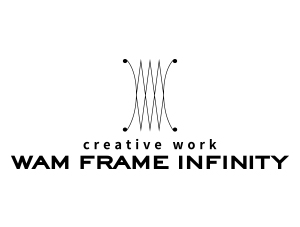+ News + a piece of Works
いくつものメガネを日常使い分けています。
作業する時、特にテーブルソーなどで木の切断をする時のために作ったメガネは、手元がしっかり見える度数にあつらえた飛び散る木の粉が入りづらい花粉用のメガネを使用します。
もちろん帽子も欠かせません;;
彫刻や正確な採寸の時など、手元をしっかり見て作業したいときは、メガネの上に手元が大きく見えるハズキのメガネをON!
特に彫刻の時、ハズキのメガネを掛けてきれいに整えた作品はメガネを外してみるととってもきれいで、ちょっと嬉しい瞬間です♡
でも、手元がしっかり見えるからとハズキのメガネをかけてお手紙を書いたことがあるのですが、大きく書いたつもりが小さな文字になってしまい、それ以降は普通に手元がよく見えるメガネを使っています。
そして、スーパーなど外出先で裏の小さな表示を見たい時や、ちょっと気軽に読みたい時、かけているメガネをわざわざ外す必要がないように、度数の低いメガネを重ねてかける「メガネ on メガネ」
あまり人様にお見せできる姿ではないですが、
「びっくりした〜!自分の目が霞んで二重に見えるのかと思ったー〜〜!」と、以前娘に言われたこともあります^ ^
普通に何もしなくて見えるのが便利
メガネは楽しいけれど、面倒でもありますね;;;
近くのお寺で月一回骨董市が開かれます。
しばらく行ったことがなかったのですが、用事で近くまで行ったので寄ってみたら、いくつかの工具類が売られていました。
今、工具を必要とする仕事をしているからこそ目に入ったのであって、きっと今までも売っていたんだろうなーと思いながら、色々あった中で役に立ちそうな綺麗なカンナがあったので購入してみました。
どういう仕事をしてくれるかはすぐにわかりましたが、名前がわからず検索。
おそらく「脇キワ鉋」と言う名前のようです。
当て木の部分を外せば、普通のカンナとしても使える♡と思ったら、残念ながら外しても使えませんでした;;;
今回、大きな額縁制作で丸く仕上げた形の外側に初めて使ってみたのですが、骨董市で買ってから研いでもいないのにとっても切れ味がよくきれいに削れて、キリッとしたラインのアクセントが簡単にでき感動でした。
「骨董市で工具を探す」という楽しみができました♡